日本人の母をもち、清朝最後の皇帝・宣統帝溥儀に連なる満洲族の父をもつ、金大偉監督のドキュメンタリー映画「天空のサマン」を鑑賞して来ました。

「サマン」とは英語のshaman(シャーマン)の語源となった満洲語です。
満洲族とは、現在の中華人民共和国の東北三省(万里の長城より北の、黒竜江省・吉林省・遼寧省)にあたる地域で狩猟生活を営んでいた人々で、清朝は彼らが建てたもの。
2007年、作曲家でもある金監督は中国東北地方に渡り、自身のルーツである満洲族の歌をもとに曲を作るつもりだったそう。
しかしいざ行ってみると、満洲語の歌を歌える人がほとんどいない。
金監督が
『これは音楽よりドキュメンタリー映画を創った方が良いのではないか』
と感じ制作を始められたのが、今回鑑賞した「天空のサマン」とその前作にあたる「ロスト・マンチュリア・サマン」
満洲語のネイティブスピーカーは高齢の方15人程度しか残っておらず、サマンの儀式が行われる村はあの広い国土の中で現在たったの3つ。
あの巨大な帝国を300年近く統治した満洲族の文化が、何故これ程まで衰退していったのか、作品を見て感じたことをシェアしながら考えてみます。
現代中国の巨大な領土のベースを作った大清帝国と、その支配階級・満洲人
中国の遼東地方で1616年に清朝皇族 愛新覚羅家の祖である満洲人ヌルハチが興した後金国。
その息子ホンタイジがゴビ砂漠以南の内モンゴル諸部を全て従え、1636年に国号を清と改めました。
さらにその息子フリン(順治帝)が1644年に万里の長城を越え、北京に入城します。
18世紀半ばには現代の南北(内外)モンゴル、チベット、新疆ウイグルを含む巨大な版図を有していた大清帝国の支配階級は、漢人ではなく満洲人でした。

帝国の公用語は満州語・モンゴル語・漢語の3つで、全土共通で通用する言語は満洲語のみ。
被支配階級であった漢人の男は、生きている間は着れなかった官吏服を、死んでからはいいだろうということで、死者に上から下まで満洲服を着せる風習が生まれました。
香港映画「霊幻道士」に出てくるゾンビ・キョンシーの服装はここから来ています。
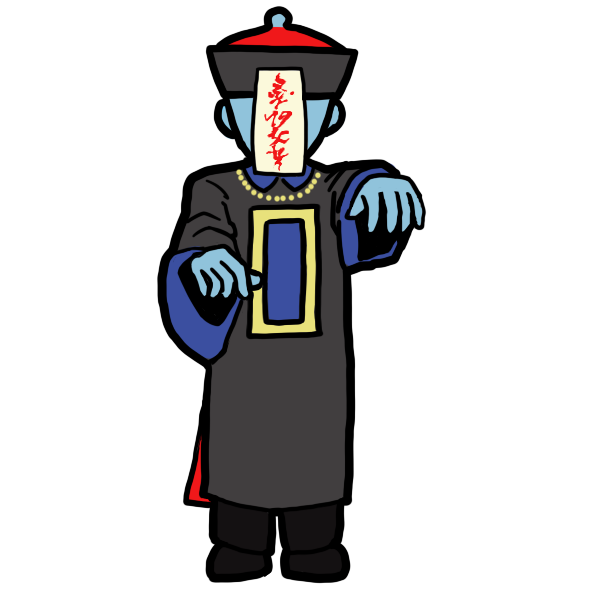
清朝の寛容な文化政策とその副作用
清朝は現地の文化を重んじモンゴル・チベット・新疆の3つを藩部と称し漢人地域と分け、種族自治を原則とします。
藩部に関しては漢人農民の移住を禁止し、商人の滞在も一年以内の制限を設けていました。
満洲人ひとりに対して漢人350人という人口比において清朝は、支配を安定させるために科挙制度、朱子学的伝統、漢字など多くの漢人文化を取り入れました。
それにもかかわらず漢人に弁髪を強制したのは、そうしないと満洲人が少数派であることが一目でわかってしまったからという説があります。

しかしその副作用として、既に18世紀初頭には満洲人のアイデンティティは危険な状態になっていたようです。
中国および内陸アジア史を専門とし、米国ハーバード大学にて教鞭を振るうマーク・エリオット教授いわく
我々が眼にする満洲人のアイデンティティに関するどの記述も、十八世紀初頭までにすでに危険な状態になっており、満洲人のアイデンティティを守るための朝廷の政策は、満洲人が自分たちの習慣を放棄し、漢人の習慣を受け入れることを阻止できなかったと語っている
朝廷は「満洲の古き道」─乗馬、弓術、質素倹約、そして満洲語の能力を重んじるスパルタ流の理想─を奨励したが、聞き入れられなかった
と言います。
信仰に関ては、古くから満洲人と関係の深かったモンゴル人の影響で、モンゴル人が信仰するチベット仏教が主流となっており、それ以前から存在するサマン文化(シャーマニズム信仰)もこの時点で著しく衰退の途をたどっていたと考えられます。
そしてさらにその百数十年後、アヘン戦争の頃にはエリオット教授いわく「次第にあまり意味のない中国的な儀礼を復唱して生き残りをはかろうとしていた」。
弁髪を下げた人間がChineseであるという一般化が起こる一方、弁髪はあるものの満洲語も騎射も怪しい満洲人が増える。
呑み込んだと思っていた側が、年月を経て呑み込まれる側になっていく。
バランス感覚を失った清朝は、20世紀動乱の時代を迎えます。
中華民国、満洲国、中華人民共和国を経て「自ら淘汰した」
1911年に起こった辛亥革命を率いた孫文のスローガンは、初めは漢民族中心のものでしたが、1912年以降「多民族的国民統合」に路線変更をします。
しかし革命後再び「単一民族国家論」に戻り、後を継いだ蒋介石はこの方針を押し進めます。
その後満洲国、国共内戦、文化大革命を経て約50年の月日が流れた現在。
2023年に話を戻します。
今回私が鑑賞したドキュメンタリー映画「天空のサマン」。
パンフレットにも書いてありましたが、出演していたひとりの老サマンが
民族のありようを捨てたのは社会によってではなく、自ら淘汰した
と言っていたのが非常に印象的でした。
文化は決して自動的に残るものではない。それを大事にする人々がいてこそ受け継がれる。
完全に失われることが現実的になって初めて覚える危機感
現在中国における満洲族の人口は約1000万人。
しかしその多くが、サマン文化を知らない。
その上冒頭で書いた通り、満洲語のネイティブスピーカーは高齢の方が15人程度いるばかり。
自分達の文化が消えゆく現状に危機意識を持った一部の若者たちは、満洲語を勉強しているといいます。
失われることが現実味を帯びてきた段階でようやくその大切さに気付く。
個人であれば自分の若さ、健康、身近な人などに対して。
集団でも個人でも、起きていることは同じかも知れません。
また修行中の若いサマンはおり、完全に芽がなくなった訳ではありません。
彼らはまだ若いにもかかわらず、インタビューを見る限り強い使命感を持って修行に臨んでいるように思えました。
サマン文化が存続するかは彼らにかかっている。
作中では、ほとんど親族だけで数日がかりで行うサマン儀式に密着したシーンがありました。
その儀式は5年や7年に一度しか開かれないもので、そんな所にカメラを招き入れているという事実が、彼らの持つ強い危機意識を物語る。
若者を指導する老サマンの興味深かった一言を紹介します。
彼は私の孫であり、後輩だ
「孫」という名詞では一族内での関係性しか表せませんが、「後輩」という名詞を使うことでもっと大きな共同体の一部としての臨場感・文化を紡ぐ者としての役割意識が表れています。
現代中国文化に残る満洲文化の影響
「天空のサマン」を制作した金大偉監督の見方はシビアで、
おそらくサマン文化は遺らない。映像としてはこれがラストになるだろう
とおっしゃっていました。
とはいえ大清帝国において満洲人の統治が300年近く続いた影響は、現代中国文明にもしっかり入っています。
例えばチャイナドレス。
あれは元々はモンゴル人や満洲人の男女が着ていたもので、襟が立っているのは寒い土地でも風を通さないため、裾がスリットになっているのは馬に跨りやすいためです。
それを天津租界の英国風仕立て屋が、女性の体形がくっきりするよう改造したものが現在のチャイナドレス。
他にも中華料理における満漢全席は清朝の宮廷から始まっており、東北料理には満洲料理も含まれます。
ということで、「天空のサマン」鑑賞後は本格東北料理を扱う中華料理屋でお昼をいただきました。
満洲料理レストランがあれば理想だったのですが、調べたところ近隣にはなかったので東北料理を中心に扱うレストラン東北大冷麺さんにお邪魔しました。
※東京を拠点とする金監督いわく、満洲料理レストランは東京にもないそうです。
お店に近づくと、自分が中国東北地方でかいだ覚えのある香ばしい匂いが。
狩猟民である満洲族は豚をよく食べていたそうなので、豚料理と狩猟色の強そうなメニューを中心にいきました。

豚の頭

豚血の腸詰め鍋

鴨の頭
鴨の頭には脳もそのまま入っていました。
脳や腸などの内臓もしっかり食べるのは、寒冷地で野菜を十分に育てられない環境でビタミンを摂取するためかと思われます。
料理の味は、現地で食べた物に近く、個人的に現地で食べた物より美味しかったです。
お客さんの9割は中国の方で、リピートして色々なメニューを試してみたいお店でした。
ちなみに金監督いわく満洲料理レストランはないものの、横浜中華街に満洲族のお菓子はあるとのこと。

甘いお菓子で、「サチマ」というそうです。
横浜に行く機会がありましたら食レポします。
このように、もとの文化(満洲文化)が消えゆくことになったとしても、様々なルートをたどって色々なところにその影響が残る。
文化にせよ価値観にせよ、大事にする人々がいなくなったら失われる。
逆にいうと大事にする人々がいれば、変容こそすれ何らかの形で受け継がれる。
文化は昔々の人々から受け取った固体ではなく、今生きている人々が紡ぎ続ける動的なもの。
「天空のサマン」はそう再認識させてくれる映画でした。




コメント