日本語にせよ英語にせよ、話者が少なく消滅が危惧される言語にせよ
言葉には、その言語が持つ世界観が表れます。
例えば普段何気なく使っている「ありがとう」という言葉。
コンビニ、飲食店、タクシー、どんなサービスを受ける時もほとんど毎回耳にする、いやおそらく耳にしない日のないこの言葉。
そして、それとは対照的になぜか最近の日本人はあまり使わない「どういたしまして」という言葉。
この2つとも、その言葉の裏にはユニークな世界観が隠れています。
世界観の表れである言葉には、思ってる以上に人間関係に及ぼす影響力があります。(後述)
言葉の選び方一つで、相手からの印象も自分の感じ方も大きく変わるにもかかわらず、私たちはそういった言葉の力に気づかないまま過ごしてしまっていることが多い。
なぜか周りに好かれる人と、なぜか周りが離れていく人、いませんか?
「また会いたい!」と思われる人と
「2回目のデートは無しでいいかな」「あの人がいるならちょっと…」と思われる人。
今回は、その違いが出るひとつの要因として「異性からも同性からもモテる世界観と言葉遣い」をテーマにお送りします。
あなたの周りの具体的な誰かを思い浮かべながら読むと、より明確に違いがわかるかも知れません。
それではどうぞ!
“モテる”とは?
かつて私が好きだった女性の中に、幼少期から30代後半になるまでずっとモテ期が止まっていない人がいました。
百戦錬磨の彼女が言っていたのは
「いい男の条件っていうのは、顔が良いとか優しいとかじゃない。
一緒にいるとエネルギーが湧いてくる。それ以外はない」
一緒にいるとエネルギーが湧いてくる。
異性からも同性からもそう感じてもらえるような、人を引きつける空気の質のようなものを、この記事では”モテる”とします。
私がこれまで会った中にも何人かそういう人がいましたが、知っている限り異性からも同性からも好かれていました。
とくに印象的だったのは、ロシアに行った時、現地で仲良くなった2人の男性。
別々の街で知り合った2人でしたが、一緒にいるとエネルギーが湧いてくるだけでなく本人のエネルギーも高かったのは共通でした。
彼らとFacebookを交換した直後から、「知り合いかも」で表示されるのは色っぽいロシア人女性ばかり。
「え、何これ?」と思いつつも気になるのでプロフィールに飛んでみると、それはすべて彼らの友達。
「あいつらいいなー」と思いながらも、ふたりの内のひとりには尊敬の念を覚えました。
ひとりは身長190cmほどある30歳すぎのイケメン。
もうひとりは身長165cmくらい?のハンサムでもなんでもない40歳前の既婚おじさん。
明らかに前者のほうがモテそうですよね。
しかし「知り合いかも」で表示されるのは後者の友達がはるかに多かったです。
そして一緒にいてエネルギーが湧いてくる度合いも、本人のエネルギー量も彼のほうが高かった。
1日一緒に散策した時があったのですが、何かと気を回してくれるんですね。
ローカルなレストランに入ればオススメのものをアレコレ教えてくれて、撮影スポットがあれば写真を撮ってくれて
「Do you want a Russian girlfriend?」と聞かれた私が「Yes」と答えたら、即座に女の子に声をかけに行って。笑
結婚してからも女性と遊び続けている点はおいといて、モテることの奥深さを感じました。
↓ロシアの飛地・カリーニングラードで彼に撮ってもらった写真

「世界をどう見て、どう言葉にするか」が言葉遣い
さてそうした、”一緒にいるとエネルギーが湧いてくるモテ”のベースには「世界をどう見て、どう言葉にするか」という世界観があります。
言葉遣いには、その言語が持つ世界観と、その人自身が持つ世界観の両方が反映されます。
例えばこの記事の冒頭で出てきた「ありがとう」という言葉。
これは元々は「ありがたし」、つまり「めったにないこと」という意味から来ています。
要は、「これは貴重な体験です」ということを表す言葉です。
つまり
- 恋人から誕生日プレゼントをもらって「ありがとう(これは貴重な体験です)」。
- 自社のサービスを受けてくださったお客様に対して「ありがとうございます(これは貴重な体験です)」。
- トラブルに見舞われた自分のために色々と動いてくれた友達。それに対して「ありがとう(これは貴重な体験です)」。
という意味になります。
やまと言葉の世界観を表す、よくよく考えてみると奇妙な表現
私たちが使う言い回しの中には、よくよく考えてみると奇妙な表現があります。
それは例えば、家でお客さんにお茶を入れる時に
「お茶を入れました」
とお伝えするのではなく、
「お茶が入りました」
という言い方をしたり
お母さんが晩御飯を作った時に
「ご飯作ったよ」
ではなく
「ご飯できたよ」
と呼びかけたり。
どちらも合わせると子どもの頃から数え切れないほど聞いている(言っている)言葉ですが、これはよく考えると、不思議な言い回しです。
自分が「お茶を入れ」ているのに、自分が料理を「作って」いるのに、どうして「お茶が入りました」とか「ご飯ができた」なんて言い回しになるのか。
それはこれらの言葉の背景には、「お茶もご飯も自分一人で作ったものではない」という大前提があるからです。
どういうことかと言うと、例えばご飯を作る時
調理に使う食材に宿る・宿っていた命だとか、育んでくれた自然や人々、またその食材たちが自分の手に届くことに携わったさまざまな人々。
それらすべてのおかげでこの料理が完成して、もちろん自分も手を加えてはいるんだけども、自分一人の力でご飯を作ったわけではない。
だから「ご飯作ったよ」ではなくて「ご飯できたよ」という言い回しになります。
「結婚することになりました」もニュアンスは同じです。
結婚という果実は、ふたりだけでこさえたものではない。
「数えきれない色んなご縁のおかげさま」という世界観が、これらの言葉には隠れています。
「ありがとう」と「どういたしまして」のセットが持つ世界観
話を「ありがとう」に戻します。
「ありがとう」の対になる、「どういたしまして」は元々どういう意味なのでしょうか?
これは「私が何かしましたでしょうか? いえ、何もしていません」という意味です。
つまり、「ありがとう」と「どういたしまして」のセットは
- 「自分が親切にするのは当たり前」
- 「何かをしてもらうことは、恵まれてる」
という世界観から来ています。
しかし私たちはついつい真逆の世界観を持ってしまいがち。
真逆の世界観とは
- 「やってもらって当たり前」
- 「自分がやることは、やってあげてる」
というマインド。
例えば車を運転していて、他の車に道を譲った時
その運転手がハザードをたかなかったら
「え、お礼なし?」
と思ったり
Amazonで何かを頼んで、2~3日して家に届かなかったら
「遅いな」
と感じたり。
いい人が多くて、何事も便利なのが当たり前の世の中(日本)では、ちょっとしたことでこのマインドになってしてしまいがち。
かく言う私もちょこちょこなっちゃいます人間だもの。
問題は、頻度としてどちらのマインド・世界観を持つことが多いかだと思っています。
理想は24時間365日「自分が親切にするのは当たり前」「何かをしてもらうことは、恵まれてる」と心の底から思えることですが、私たちは聖人君子ではないのでそれは現実的には難しい。
お腹が空いてる時や睡眠が足りてない時は、やっぱりイライラしやすくなっちゃう。
でも、「何かをしてもらうことは恵まれている」と思う人の方に自然と人は集まるし、集まった人たちのエネルギーも湧いてくるのも事実。
そこで、いきなり完璧を目指すのではなくて、時間的余裕をもって意識的に変えられる言葉遣いからひとつずつ・少しずつ変えていくやり方なら取り組みやすいです。
例えば自分が家にいる時に怪我をしてしまって、外で仕事中のパートナーに絆創膏を買ってきてもらうことを頼む時
「絆創膏買ってきて」
と一言だけメッセージを送るのか
それとも、メッセージを送る前にひと呼吸おいて
「お疲れ様です。怪我をしたので帰りがけに絆創膏買ってきてもらえると嬉しいです」
といったメッセージを送るのか
表面的に伝えていることは一緒ですが、相手が持つ印象と、繰り返した時の関係性へのインパクトはだいぶ変わります。

すべての言葉遣いをいきなり変えられなくても、メッセージのやりとりなど、時間的余裕をもって意識的に変えられるところからひとつずつ、少しずつ変えていく。
自分の口癖を観察してみて、モテる世界観の言葉遣いは増やしていって、そうではない言葉遣いは減らしていく。
新しい言葉遣いに感情が追いつき、世界観も変わっていきます。
「新しい言葉遣いに感情が追いつく」の意味がわからなければ、一番ムカつく人に「ありがとう」と直接言ってみてください。
「言葉遣いに感情が追いつく」を体感出来ます。
盲点になりがちな、自分の口癖や言葉遣いから世界観を変えて”モテ”ましょう!
感想やご質問、掘り下げてほしいところ等あればお気軽にコメントやDMください。それでは!


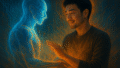
コメント