「30歳を過ぎたら、何事にも新鮮味を感じる感性が落ちる」
「頭が硬くなる」
「覚えが悪くなる」
といったような言葉。
一度は耳にしたことがあるかも知れません。
30歳をひとつのボーダーラインとする考えは古今東西にあり、儒学の祖である孔子の言葉をまとめた書物・論語においては
三十にして立つ
茶道三千家の祖・千利休の言葉では
十五より三十まで万事を師にまかするなり。
三十より四十までは我分別を出す、…(中略)…十のもの五我を出すべし
としていました。
中世ヨーロッパでは人の一生を10年ごとに分け、
20 years a youth
20歳は若者30 years a man
30歳は一人前の男
としていました。
もしあなたが30歳を過ぎているなら、この言葉たちをどう感じますか?
20代以前と、何かが変わったでしょうか。
もしあなたがまだ30歳を迎えていないなら、「30になる」ことをどう捉えていますか?
その後には、何かが変わるとイメージしているでしょうか。
変わるとしたら、何が変わるのでしょうか。
そもそもこの30歳ボーダーライン説に何か根拠はあるのか?
脳科学、認知科学の知見を借りてこの説を掘り下げてみます。
脳科学における「30歳成人説」
脳科学では、「脳が成熟するのは30歳以降」とする研究があります。
要約すると、
私たちが何かを考えたり動いたりする時、脳の中ではこのネットワーク(軸索)を通じて神経伝達物質のやり取りをしています。
はい、ややこしいですね。
こんなイメージです。
- 軸索(ネットワーク)=高速道路
- 脳の神経細胞=高速道路のサービスエリア
- 神経伝達物質=高速道路を移動してやりとりされる荷物
何かを繰り返し練習すると、脳の中の同じ回路を神経伝達物質が繰り返し通ります。
すると脳はその回路を「よく使う道路」として認識します。
そしてよく使う道路ほど、舗装を厚くして整備します。
舗装された結果、荷物(神経伝達物質)が移動する時間が短縮され、慣れたことは簡単にできるようになります。
逆にいうと、使わない道路は舗装されません。
例えば私たちは「日本語を話す」という道路はたくさん使っているので、料理をしながらでも、パソコンで仕事をしながらでも簡単に話すことが出来ます。
しかし、同じ条件で「英語を話す」となるとどうでしょう。
日本語よりもはるかにシンプルな体系の言語であるにもかかわらず、難易度が格段に上がることを感じたかも知れません。
これが、よく使う道路とあまり使っていない道路の違いです。
この高速道路のネットワーク(神経伝達のネットワーク)の束が、少なくとも30歳を迎えるまでは脳全体に行き渡っていないというのが先ほど挙げた英文記事の主旨です。
米国のスタンフォード大学で教鞭をとる神経科学者アンドリュー・ヒューバーマン博士は25歳をボーダーラインとしていますが、言っていることは概ね同じ。
10:25~ Everything changes at 25
17:21~ Brain space
要約すると、
25歳およびその±2歳までは消極・受け身の経験によっても脳のネットワークが変わる。
必要とされるものは強化され、不要なものは淘汰され。
それ以降の、脳の中でひとしきり整備された道路のつながりを変えたいのであれば、意識的な努力・フォーカスが必要。
経験により脳のネットワークが変わる性質(神経可塑性)自体は死ぬまで備わっている。
つまりボーダーラインが30歳にせよ25歳にせよ、その前後で学習の条件が大きく変わる。
学習とは知識やスキルの習得だけではなく
運動を始めることや、禁煙や、考え方を変えることなど、行動のパターン・思考のパターン・感情のパターンに手をつけることも含まれます。
ボーダーラインを30歳だとして、それを過ぎると意識的な努力・フォーカスなしでは脳のネットワークが変わらない。
(ただしヒューバーマン博士いわく、強いネガティブな感情を伴う経験によっては変わる)
これはつまり、30歳以降意識的な努力をしない・フォーカスを作らない人は
人生の最初の30年間でたまたま効率の良かった行動パターン・思考パターン・感情パターンで
ひたすら過去の記憶を再生し続けるだけの固体と言うことも出来ます。
30歳ボーダーライン説は、そこから両極化するという意味では強ち間違っていないかも知れません。
25歳以前と以後の、フロー状態(およびゾーン)への入りやすさの違い
「フロー状態になる」
「ゾーンに入る」
という言葉があります。
フロー状態とはこちらの記事↓でも例を添えて書きました通り、時間の感覚がなくなるほど対象に没頭・没我している状態で、その最も深い状態がトップアスリート等が体験するゾーンといわれるもの。

さて上述のヒューバーマン博士はこうも言っています。
25歳までは、私たちの脳は高い神経可塑性を持っているが、大人がするようには自分たちの生活・人生をコントロール出来ない
脳において自分の生活・人生をコントロールする上で重要な役割を担うのは、理性を司る・しかし成熟の最も遅い部分、前頭前野。
この前頭前野が成熟するのは25歳頃といわれています。
先ほど紹介したフロー状態になると、前頭前野の活動が低下します。
フロー状態になると時間の感覚がなくなりますが、それは脳の一部の機能を停止して「一瞬」に取り込むデータ量を増やすことで、時間の流れが極めて遅く感じられるようになるためです。
若い人、その中でもとくに子どもは、前頭前野が発達しきっていないので実はフローに入りやすい。
あなたは子どもの頃、狂ったように遊んでいた記憶はどれくらいありますか?
フローとQOL
↑こちらの本の中に、
QOLの観点から言って、日常生活の中でフローに入る機会の最も多い人が一番幸福
という言葉があります。
つまり若い人や子どもはフローに入る・幸福を感じることについても、学習と同様「大人」に比べ意識的努力を必要としない。
20代後半から早くも
若い時に戻りたい
と言い出す人は、そのあたりの変化を感じているのかも知れません。
ただそのまま意識的な努力もせずフォーカスも作らないのであれば
フローに入りづらくなった状態で過去の行動・思考・感情パターンを繰り返すだけの固体として歳を重ねることになります。
さらに言えば肉体も年齢に応じて変化し、自分を取り巻く社会環境も変化し続ける。
これらを考慮に入れると
繰り返し続けるのはただの過去ではなく、劣化した過去と言えるかも知れません。
25歳を過ぎてからも幸福度と脳力を上げ続けるメタスキル
幸福につながるフロー状態になる条件は7つあります。
①明確な目的
②自律性(自分で決めてやっている感覚)
③取り組む事が限定されている。集中できる
④直ちにフィードバックが得られる
⑤今の自分にとって、程よく難易度が高い
⑥目的だけでなくその活動自体に本質的価値を感じる
⑦行為と意識の融合(自分は何か大きなものの一部と感じる)
25歳を過ぎた「大人」で幸福度も脳力も高め続けられる人は、たまたまこれらの条件がそろった環境に居続けられるラッキーな人か、意識的にこれらの条件を整え続ける人。
一時的に運良くそういった環境に身を置けたとしても、自分でその条件・環境を整えられなければフロー状態を再現出来ない。
7つの条件をいきなりすべて満たすのは難しいなら、ひとつずつ、少しずつ手をつけてみる。
例えば
②自律性(自分で決めてやっている感覚)
を高めるのであれば、何かを決断する時「私はこれをやると決めた」と心の中で言う。
毎日する決断でいうと、着る服を決める時や、ランチで何を食べるかを決める時、通勤するルートを「選ぶ」時。
地味ですが、これを繰り返すと惰性でやっているものの中にも、実は選択肢がたくさんあることに気付きます。
通勤ルートも、毎日そのルートである必要はどこにもありません。
次に例えば
③取り組む事が限定されている。集中できる
これを満たす環境を用意することを始めるなら、例えば本を読む時はスマホは電源を切るか、違う部屋に置く。
そしてキッチンタイマーを25分もしくは52分にセットし、それが鳴るまでは一心不乱に読み続ける。
(セットする時間についての参考記事はこちら↓)
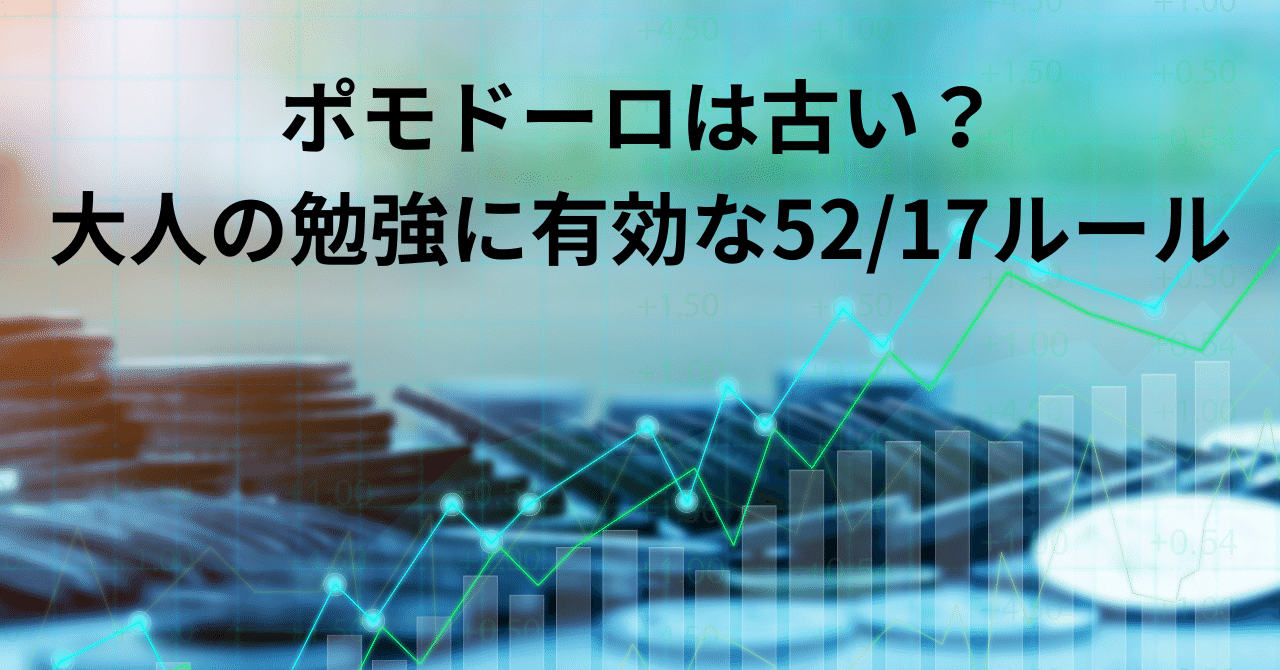
たまたま幸せになるか、過去の記憶を再生し続けるかというギャンブル人生にしないためにも、フロー状態になるための環境設定能力はきわめて重要なメタスキル。
ボーダーラインを25歳にするにせよ30歳にするにせよ、この辺りの年齢から外面的なものに限らず内面においても差が出てくる。
30歳ボーダーライン説は、そこから両極化するという意味では強ち間違っていないので、フローに入る条件を整えるメタスキルが大事というお話でした。
感想やご質問、掘り下げてほしいところ等あればお気軽にコメントください!それでは!




コメント