こんにちは、テツヤです。
本を読んだりYoutube動画で何かをインプットしたりして
「面白!」
「あ、なるほどな」
「そういうことだったんだ勉強になるなー」
とその場では思うものの
1週間後にはその内容をほとんど忘れてしまったり、覚えていても次の日からの行動は何も変わらなかったり、なんて経験ありませんか?
私はむっちゃくちゃありました。
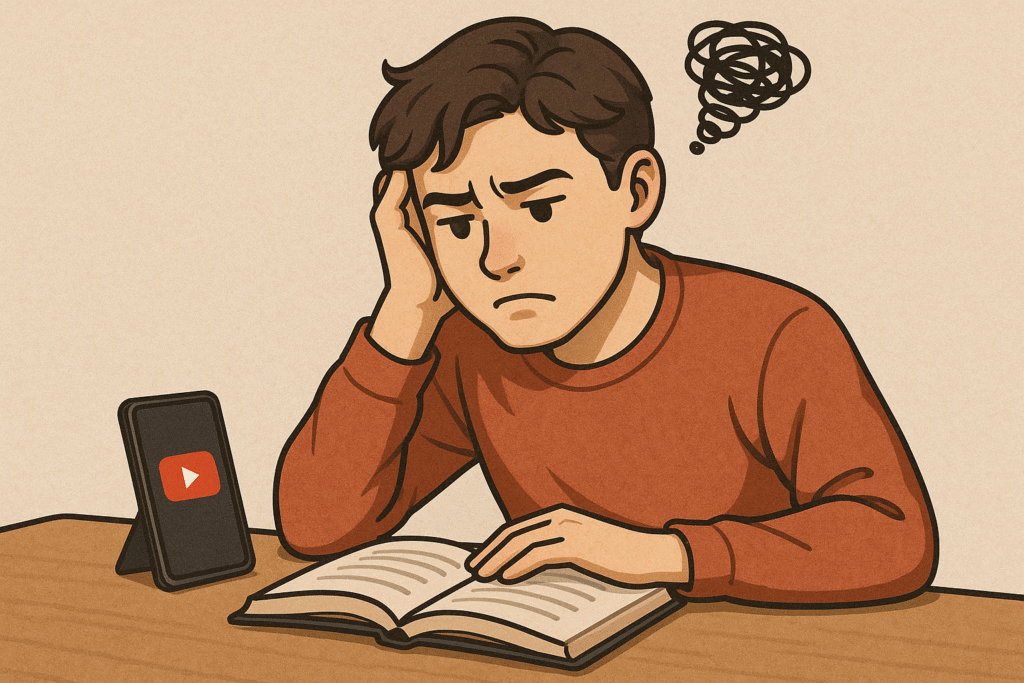
本を読んでる間は楽しい。
知識もちょっとずつ ついて来てる。
でも得体の知れない閉塞感が常につきまとっていて拭えない。
インプットすることで知識は手に入ったかもしれないけど、根本的には変わっていない。
頭でっかちになるだけで、やること(体や心の動き)が変わっていない。
「えっ、あれからもう1年経ったの?」
根本的な変化のなさに鬱になり、インプット自体やめたくなることもありました。
そんな頭だけがデカくなっていく状態に嫌気がさし、心や体(行動)もバランス良く発達させる学びを得ようと手探りで色々とやりました。
本を読む量をガクンと減らして、4ヶ月の海外周遊も含め色々な行動をする中で
「本当の学び」についてひとつの腑に落ちる表現にたどり着きました。
(色々な行動についてはこちらに詳しく書いてます↓)
今回のテーマは、知識を増やすだけの学びと 望む現実をつくるための学びの違いについてです。
「望む現実をつくるための学び」とは
私はかつて、こう感じていました。
「いくら情報を詰め込んでも、現実が変わっていかない。
毎年同じことを繰り返してる。でもどうすればいいかわからない…」
ここでいう情報とは、本とかセミナーとか、そういった知識的なものに限らず
自分が動くことによって五感で得る情報も含めます。
例えば
- 観光地で絶景を見る(おもに視覚情報)
- 好きなアーティストのライブに行く(おもに聴覚情報)
- 三つ星レストランに行って美味しいものを食べる(おもに味覚情報)
これらは五感で得る情報です。
海外旅行にせよ国内旅行にせよ、行ってる最中は楽しいんです。
友達とワイワイやれて色んな所に行けて、美味しいご当地グルメを食べて…
でも日常に戻ると「このままでいいのか」という心のモヤモヤが拭えない。
好きなアーティストのライブに行ったり面白そうなイベントに顔を出したりして、娯楽に浸る。
全身で音を感じて、五感で刺激を浴びて。
でもそれが終わって普段の生活に戻ると、クスリが切れたように虚無感を覚える。
そんな得体の知れない閉塞感が消えないのは
「あること」がずっと変わっていないのが原因でした。
その「あること」とは、自分の中の優先順位づけです。
自分にとって何が重要で 何が重要でないかの優先順位づけ。
つまり
何が大事で、何が後回しでもいいのか
何に反応して、何をスルーするのか
その判断をしている見えないアルゴリズム。言い換えると、自分を動かすアルゴリズム。
それが更新されていないと、いくら情報を詰め込んでも現実は変わらない。
言い換えると、どこへ行っても何を観ても現実は変わらない。
「望む現実をつくるための学び」とは、自分を動かすアルゴリズム=自分の中の優先順位づけを更新することを言います。
次の章で具体例を挙げます。
「望む現実をつくるための学び」が出来たかどうかを知るには?
知識を増やすだけの学びではなく、望む現実をつくるための学び。
それができたかどうかのわかりやすい基準がふたつあります。
それは、
- 動きが変わったか
- 判断基準が変わったか
です。
例えば私は、見た目が どストライクなだけでアプローチした異性に振り回されて
「つらっ。次の人はちゃんと内面も見よう」と思ったことがあり
それ以来見た目だけで異性を選ばなくなりました。
これは、わかりやすく優先順位づけが変わった=望む現実を作るための学びが出来た例です。
こういった例も、判断基準や動きが変わっている=自分を動かすアルゴリズムが更新されています。
この定義でいうと、「学び」の機会は本や動画、セミナーに限らず、ありとあらゆるところに溢れていることになります。
毎日行く場所にも、毎日会う人との会話の中にも。
そう考えると、あなたのこれまでの人生の中で最も大きかった学びは、本やセミナーから得たものとは別のものではないでしょうか。
「学び」を得るためのアプローチの一例
ではそういった「学び」を得るためにどうするのか。
先ほど言った通り、インプットの機会はありとあらゆるところに溢れているということを大前提として
インプットする時の準備で出来ることは
例えば
- インプットを始める前の準備として、今解決したい問題をピックアップして、あらかじめフォーカスを作っておく
- インプットを挟んだビフォーアフターでどんな考え方・理解が変わったか、どんな行動を変えるかを言語化する
- アウトプットする機会を作ってからインプットする
などがあります。
とくに3番のアウトプットする機会は意識して作らないと、インプットに偏ってしまいがち。
アウトプットの重要性については別記事↓で語ったのでそちらに譲るとして
▶︎学んだ気になって終わるインプット中毒の人生から脱出する方法
2番を少し掘り下げます。
インプットした後に、具体的な動きも判断基準も変わっていないのであれば
「望む現実をつくる学びにまったくなっていない」ことになります。
それを避けるために、わざわざ「どんな行動を変えるか」まで言語化します。
ここで気をつけるのは、実際にはやらないカッコイイ行動を書くのではなく
どんなに小さくてもいいから、現実に実行可能な行動のアイデアまで落とし込んで言語化することです。
例えばこの記事を読んで、「アウトプットする機会を作ろう」と思ったとします。
音声配信やブログを始めるのはハードルが高いと感じているのであれば、XやInstagramでの発信から始めることも出来ますし
それもハードルが高く感じるなら、友達との会話の中で話してみる
それもハードルが高いなら、自分の部屋でひとり語りする
というように、実行可能な行動まで落とし込む。
発表すれば人が褒めてくれるけど実行出来ないアイデアより
パッとしない小さいことだけど、実行出来るアイデア。
望む現実をつくるための学びが出来たかどうかの基準のひとつ
「動きを変える」ことにフォーカスしたのがこのアプローチです。
この話を聞いて、もしかすると
「小さいアイデアなんかどれだけ実行しても現実変わらないよ」
と思ったかも知れません。
その実行アイデアを形を変えずに繰り返すだけで、難易度をずっと上げないのであればおそらくその通りです。
難易度を上げる?
難易度を上げる、そうゲームのようにです。
マリオでもドンキーコングでも、チュートリアルのためにあるようなステージ1-1をずっとやってると飽きちゃいます。
何回もクリボーにぶつかったり穴に落ちたりしながらプレイに慣れ、ステージをクリアする。
ステージは進めば進むほど難易度は上がっていき、その程よい難易度が私たちを楽しませてくれる。
これと似たような状況を、意識的に作ります。
先ほどの例で言うと、部屋でひとり語りをすることからアウトプットを始め、慣れてきたとします。
しかしそれを何十年続けても、自分の声がひたすら虚空に消えていくだけ。
その慣れと虚しさが相まって飽きを感じた時に、その行動をやめるのではなく、難易度を上げてみる。
それも1回上げるだけではなく、スーパーマリオでステージを進んでいくように
慣れや飽きを感じる度に難易度を上げ続ける。
ひとり語りに慣れたら、友達に話すことを始めてみる。
友達に話すことにも慣れてきたら、友達の行動が変わることを目標に話してみる。
例えば本を読んでそのアウトプットとして内容を友達に話すなら、友達がその本を買う(行動が変わる)ところまでいくように話をする。
それにも慣れてきたら、そのコミュニケーションスキルをひっさげてフルコミッションセールスの副業にチャレンジしてみる。
このように、最初の実行アイデアは小さなものでも、難易度を上げ続ければ複利が利いて望む現実をつくるのに十分なインパクトを発揮します。
知識を増やすだけではない、望む現実をつくるための学び。
インプット後に増える知識ではなく、変わる動きと判断基準にフォーカスしてみると、「学びの質」が格段に変わる、というお話でした。
感想やご質問、掘り下げてほしいところ等あればお気軽にコメントやDMください。それでは!



コメント