こんにちは、テツヤです。
新しい分野について学び始める時、どんな風に進めていますか?
本を何冊も読んだり、関連するYouTube動画をいくつも見たり、セミナーに参加したり。
たくさんインプットしてるのに
「量の割に、あまりしっくり来てないな…。もっと効率のいいやり方がある気がする」
そんな風に感じた経験はありませんか?
私の場合、「アウトプットすると時間が減る」と思い込んでいたことがその大きな原因のひとつでしたが
▶︎学んだ気になって終わるインプット中毒の人生から脱出する方法
もうひとつ、学習においてアウトプットと同じくらい重要と言える要素があります。
それが、学ぶ順番。
同じ材料を使っても、料理の手順が違えば味が変わってしまう。
例えばチャーハンは、卵をいつ入れるかでそのクオリティがガラッと変わります。

同じ教材をそろえても、手をつける順番次第で理解の深さが劇的に変わる。
でも学校でも会社でも、誰もこの最適な学習順序の見つけ方なんて教えてくれません。
そこで今回は、生成AIと制約理論(後述)を使った学習設計で、効率的に学びを深めるインプットの順番を見つける方法についてお届けします。
それではどうぞ!
ざっくり版「制約理論とは」
まず、制約理論について簡単に説明します。
制約理論とは、有名なビジネス小説『ザ・ゴール』の著者であるエリヤフ・ゴールドラット博士が唱えた理論です。
考え方は超シンプル。
入口・通路・出口というメタファーを使って説明します。
目的を出口、前提条件を入口として、その間を通路とします。
そして、入口から出口への流れ=フローをいかに滞りなくスムーズにするかを考える理論です。
これを学習に応用すると
- 新しい分野のインプットのために用意した、本や体験の機会(前提条件。入口)
- 新しい分野を深く理解する(目的。出口)
その出口に向かう流れの中で、どこで詰まりが起こっているか、どうしたらフローがスムーズになるかを考慮した上で学習の手順を決める。
今回お話しするのは、その手伝いを生成AIにやってもらうというものです。
事例:初めて歌舞伎を学ぶにあたって
実際に私が試した例をお話しします。
来月、縁あって生まれて初めて歌舞伎を観に行くことになりました。
その予習として2025年9月現在上映中の映画『国宝』を鑑賞し、さらに歌舞伎を学ぶための本3冊を用意しました。

用意した3冊は
- 『知識ゼロからの歌舞伎入門』(基礎知識)
- 『絵で知る歌舞伎の玉手箱』(小道具や演目の解説)
- 『歌舞伎と日本人』(文化論)
最初は「3冊全部読んでから映画を見て、最後に実際の歌舞伎を鑑賞する」つもりでした。
しかし生成AIに制約理論の考え方を学習させて相談したところ、まったく異なる順番が提案されました。
生成AIが提案した「目からウロコ」の学習順序
私が使ったのは、NotebookLMという生成AIです。
NotebookLMはもともとは、ノートを使ったAI学習支援ツールという位置付けで開発されました。
研究者が論文を読ませてその内容を深めるために使われたりしています。
まず、このNotebookLMに制約理論に関する資料をアップロードして学習してもらいました。
その上で、自分の学習素材(3冊の本、映画、観劇する歌舞伎)の情報と「歌舞伎を深く理解する」という目的を伝えて、最適な学習順序を導き出してもらいます。
NotebookLMが提案してくれた順番は
- 『知識ゼロからの歌舞伎入門』を読んで基礎知識を身につける
- 映画『国宝』を鑑賞して、視覚的な参考材料をたくさん得る
- 視覚的な参考材料を得た上で、『絵で知る歌舞伎の玉手箱』で小道具や化粧、服装の意味を知る
- 実際の歌舞伎を鑑賞する。基礎知識と視覚的イメージが整った状態で、五感や感情を伴った体験をする
- 最後に『歌舞伎と日本人』で文化論を読む。鑑賞中に生じた疑問や興味に対して、体験と結びついたより深い理解を得る
この順番の妙は、各段階で得た知識や体験が、次の段階の詰まりを解消する設計になっていることです。
映画や実際の歌舞伎鑑賞の間に本を挟むことで、抽象的な知識が具体的なイメージや体験と結びつき、最後の文化論も実体験に基づいて理解できるようになる。
面白いことに、制約理論を学習していないChatGPTに同じ相談をすると、また違う順番が返ってきました。
同じ生成AIに同じ質問をしても、毎回同じ答えが返ってくるわけではないことを差っ引いても
これは生成AIに何を質問するかと同様に、何を学習させるかも重要だということを示しています。

生成AIに学習順序を相談する具体的なステップ
生成AIに最適な学習順序を相談する具体的なステップはこちらです。
- 学びたい分野を1つ選ぶ
- その分野で利用可能な教材をリストアップする 本、動画、体験、セミナーなど、教材として使えるものを洗い出す
- 生成AIに思考フレームを学習させる NotebookLMやChatGPTにお気に入りの思考フレーム(私の場合は制約理論)の資料をアップロードし、学習させる
- 思考フレームを学習した生成AIに相談する 学習の目的と利用可能な教材を伝えたうえで、学習順序の最適化を相談する
ちなみに私がNotebookLMを選んだ理由は、他の生成AIに比べ、学習させた思考フレームに忠実に沿って答えを返してくれるからです。
ChatGPTやClaudeは創造的で柔軟な答えを返してくれる代わりに、彼らが他の思考フレームや一般知識を使うことが邪魔になる時があるので、特定の枠組みに忠実な答えが欲しい時はNotebookLMを使うようにしています。
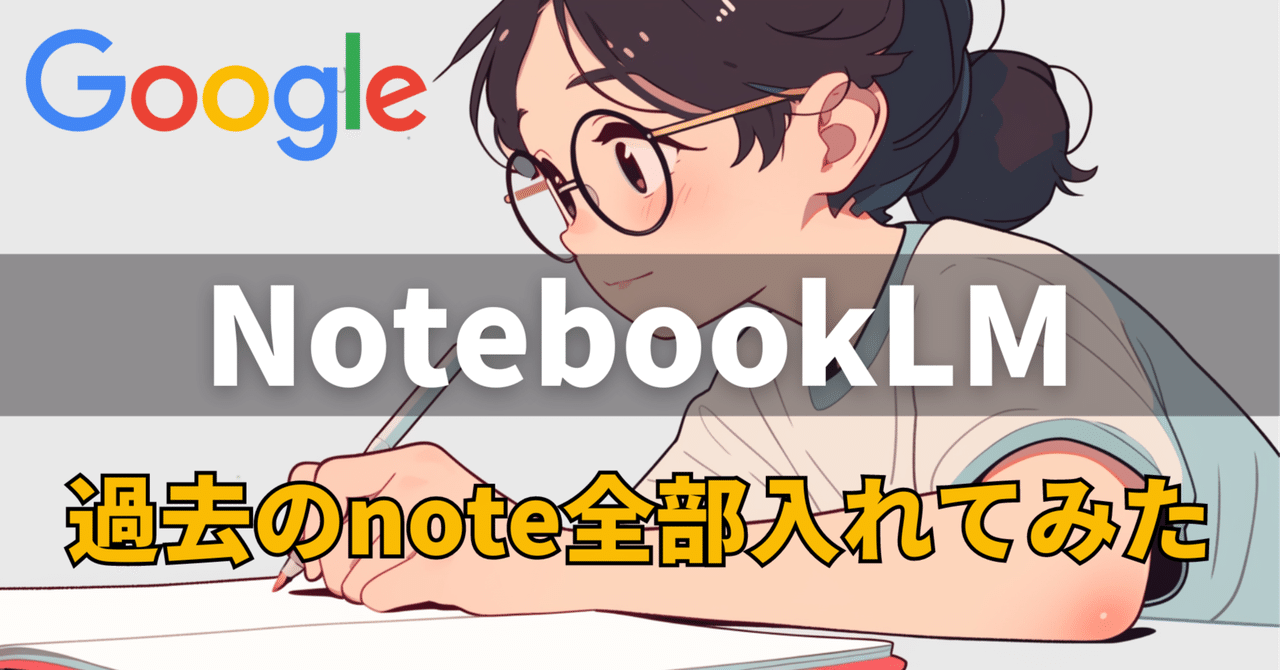
変わる 学習への向き合い方
歌舞伎体験は来月ですが、すでにこの準備段階で学習への向き合い方が変わりました。
あなたがもし「なんとなく非効率な気がする…」という学習の停滞感を感じているのであれば
取り組む順番を変えてみると、一気に解消されるかも知れません。
どの教材で学ぶかと同じくらい重要な、どの順番で学ぶかについてのお話でした。
感想やご質問、掘り下げてほしいところ等あればお気軽にコメントやDMください、それでは!



コメント